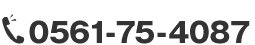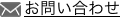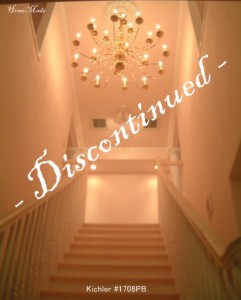今朝、名古屋市緑区のお客さんから車庫スペースを手直ししたいというご依頼を頂いて、お邪魔してきました。
2台分の屋根のない駐車スペースと1台分の物入れが存在しているところを、古い物入れを撤去して、大きな屋根兼ウッドデッキを車庫の上に載せたいらしい。
以前、このお客さんの紹介で、並びのおうちで同じような車庫デッキを造らせてもらったので、それをイメージして頂いているようです。予算的にちょっと厳しい感じですが、どうやったらご希望に近いものが出来るか、考えなければいけませんね。
打合せ後、その並びのおうちも見に行きましたが、ここのご主人が結構まめな人でご自身でデッキに防水塗装をしたり、古くなった柱材を自分で取り替えたりして、メンテナンスをして下さっています。(塗料は、PARAのティンバー・ケア、アクリル・レインコートを使用)
腐りにくいレッド・シダー(米杉)で出来ていますが、天然素材は環境に左右されますし、一生涯ノーメンテナンスなどというものはありません。
新しいSPF材だと、ちょっと色の違いが気にはなりますが、これはこれでいいのです。腐ってみすぼらしくなってからでは、メンテナンスにお金が掛かってしまいますし、運気にもよくありませんからね。
日本のお父さん、頑張って下さいね!輸入住宅のメンテナンスでお困りの方は、お問い合わせ下さい。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。