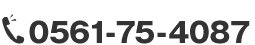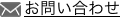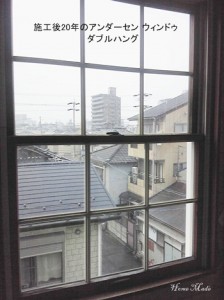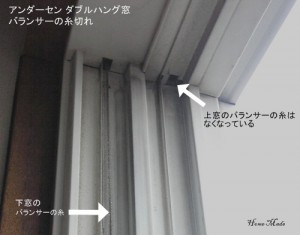来週、カナダからレンガ職人がやってきて、外壁のレンガ積みが始まる岐阜市 N邸。
そうこうしているうちに、全館空調等のダクト配管も終わり、セルロースの断熱材を入れたり、ドライウォールの下地施工が始まろうとしています。まあ、そんなタイミングですから、ドライウォールの施工について少しおさらいをしてみましょう。
日本の大工は、910mm x 2,430mmの石膏ボードを縦長に張るというのが基本です。でも、本来の石膏ボードは、写真のように横長に張らなければ、全く意味がありません。
石膏ボードを生み出した欧米では、1,220mm x 2,430mmの少し大きめのボードを横に寝かせて張るのが常識ですから、縦長なんかに張ろうものなら大工のボスに厳しく怒られることとなるでしょう。
日本では、天井までの高さが2.4mというおうちが一般的なので、縦長に張ると上から下まで1枚のボードで張ることが出来ます。ですから、無駄なく簡単に施工出来るし、材料のロスも少ないと日本人は考えました。
ただ、石膏ボードが日本に導入された時に、一見非効率に見える横張りの施工が欧米で行われているのかを、何故しっかり考えなかったのでしょう。また、導入した人が英語が苦手でいい加減な理解しか出来なかったのかも知れません。
何がいけないのかと言えば、ボードの切れ目(ジョイント)が天井から床まで縦一直線で入ってしまうことです。それも910mm幅で何本も壁に入る訳です。
賢い人ならお分かりでしょうが、ジョイントというのは強度が一番出ない部分で、クラックが入る一番の弱点ですから、建物が自分の重さによって床方向に縮もうとする時、圧縮によって縦のジョイントにクラックを生じます。ですから、私たちは部屋のコーナー部分などのどうしても縦にジョイントが入らざるを得ない場所以外は、極力縦ラインのジョイントを作りません。
でも、横にしたって1枚のボードだけで壁面を作らない限り、縦のジョイントは出てしまいますよね。(まあ、そんな大きな石膏ボードは、存在しませんが・・・)
そこで、欧米や私たちのようなドライウォールのプロは、レンガを積むように互い違いにボードをレンガ張りするのです。そうすることで、上になるボードの縦のジョイントの部分を下の一枚もののボードが下支えする形が取れるのです。つまり、ボードの縦ジョイントが上から下まで垂直に通ってしまうことがないように気を遣って施工しているんですね。(外壁のレンガ積みでレンガを揃えて積まないのは、そういう理由です。ジョイントを揃える目地のやり方は、イモ目地と呼ばれます)
あと、ボードは出来るだけ1枚で使うようにしますから、写真のように窓やドアの部分をくり抜くようにしてボードを張ります。(写真のオレンジのラインの部分です)
また、テーパーボードや専用の紙テープ、天然石膏のパテを使って、ジョイント部分を強化することも忘れてはいけませんよ。これらの材料のことをよく知りたい方は、右にある「カテゴリー」の「ドライウォール」をクリックするといろんな記事が出てきますから、そちらをご覧下さいね。
そうそうドライウォールを知らない建築屋さんでは、こうした下地施工をする前に既にフローリングやドアといった内装材を取り付ける造作工事をやってしまっているところもあるようですが、これも論外の施工手順です。
どうか皆さん、手を抜かないで美しいドライウォールを目指して下さい。また、こうしたボードの下地施工は、クロス張りの時でも同じように必要な作業です。正しい材料、正しい施工の両方が揃ってこそ長く愛着の持てる輸入住宅になるのです。安くても、なんちゃってドライウォールはダメですよ(笑)
こうした私たちの考えや建築に共感され、施工を希望される方は、ご相談下さい。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。