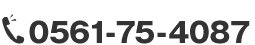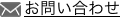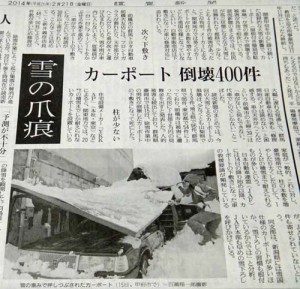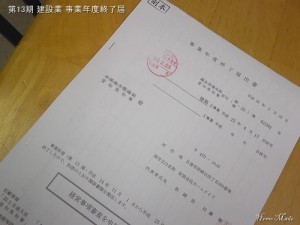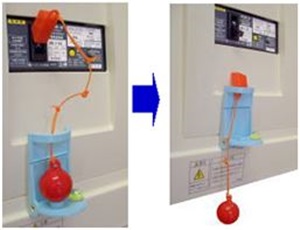年度末まであと1ヶ月。3月末までに家を建てないと消費税が5%から8%にアップしてしまう。
昨年9月末までに新築の契約をした人は、竣工が4月にずれこんでも5%のままなんだけど、それ以降に契約した人は、どうしても3月末までに完成しなければ困るといった意識があるようだ。
今日、ある水道業者さんと話をしたんだけど、彼は大手ハウス・メーカー Mホームの仕事もしているそうな。彼曰く、今そのメーカーの工期は、何と2ヶ月。そして、駆け込み需要を取り込んだ為に、1月着工3月引き渡しの物件が強烈にあって、現場は普段ではあり得ない物凄い状況になっているらしい。
大体、基礎をコンクリートで作るにしても10日~2週間は掛かると思っている。また、コンクリートがしっかり中まで乾くには、更に1週間以上は養生期間として放置しておく必要があるのだ。
2ヶ月の期間で着工から完成までの全てを行うとしたら、そういった必要な時間を無視する他はない。
また、3月末にどうしても引き渡しをしなければいけない住宅がたくさんある為、9月末までに契約を済ませている先約のお客さんの家を放っておいて、3月末までの家に大工や協力業者を集中的に投入するといった戦略を取っているというのだ。
大工というものは、人によって腕が違う。また、施工の仕方も同様に違うのに、いろんな大工が同じ現場に入ったら、統一感のあるきれいな仕事など出来るはずがない。突貫工事で尚且つ質を落としてまでも、本当に3月末までに完成させる必要があるのだろうか。
だって、この後何十年も住もうというおうちではないか?お金に代えられない何かを失ってはいませんか?
当然の如く、先約のお客さんからは、現場に職人さんたちが入っていないことにクレームが付くし、突貫工事で荒くなった仕事に対しても、引き渡し間近のお客さんから文句が出る。まさに、マイナスのスパイラル。現場も人も全てがネガティブな状況がそこにある。
以前記事に書いたけど、消費税がアップした後の減税措置の方が、3%の増税分より大きい人も少なからずいるのだ。勿論、借入額の大小や年収によっても、その損得は変化する。だけど、どっちに転んでもどっこいどっこいになるように政府はうまくコントロールしているんだよね。
いいように業界や政府の口車に乗せられているのは、実は3月末で焦っているお客さんに他ならない。
何とも気の毒な話ではあるが、その会社との契約を決断したのも、住宅メーカーに非常識な工期での施工をお願いしているのも、その方たちなんですよね。
電化製品のように、どこに行っても同じものというなら話は別だが、金額だけで決めていいものとそうでないものとがあるはずだ。さて、住まいはどっちなんでしょうねぇ?
それにしても、住宅業界ってひどいですねぇ。私はそういう業界に一石を投じたいと思います。
関連記事: う~ん、過渡期とは言え、やっぱり変かも!
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。