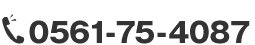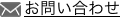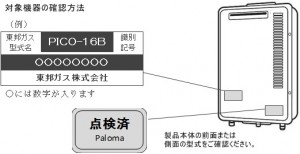省エネや地球温暖化対策など、環境に対する技術や性能を謳う大手住宅メーカーが多くなってきた。
その中で特に最近数値として取り沙汰されるのが、Q値とC値。この数値で表す性能が高ければ、素晴らしいというのが彼らの主張である。また、それを重視する消費者が多くなってきていることも、この競争を加速される要因となっている。
まずは、その値が表す意味を簡単に説明することにしよう。
Q値:家から逃げる時間当たりの熱量を、家の床面積で割った数値
C値:家全体にある隙間面積を床面積で割った数値
Q値は、床面積の大きさの割に、外部と接する屋根や外壁面を小さくして、その外部接点の断熱を高めることが出来れば、高い数値(高得点)をたたき出すことが可能となる。C値も同様に、床面積の割に隙間を少なく出来れば、高い数値となる訳だ。
だが、ここにはいろいろなマジックが存在する。このことをしっかり理解出来ないと、カタログ数値に惑わされた家づくりをしてしまうなんてことにもなりかねない。
まず言いたいのは、Q値は机上の論理で、実測されたものではないということだ。また、注文住宅のような個別の間取りで計算するのは、面倒で相当な時間も掛かるので、殆どの住宅は計算が行われない。
つまり、ある1つの事例(建物)を基準にして、その建物だけについて紙の上で計算しただけの実態性の乏しい数値という訳だ。
そして、断熱材の入れ方や気密シートの張り方など、実際の施工の精度の善し悪しによって熱損失の度合いは変化するので、実測されない数値には意味はないと言わざるを得ない。
(現場の大工や職人が、学者のようにQ値を考えて施工するというのは、現実無理である。特にローコストで請け負った職人は、どうしたって仕事が早くて雑になる。あってはいけないが、設計仕様と異なる偽装?施工が行われれば、机上計算は全く無意味となってしまうのである)
また、建物で一番熱損失が大きいのは、窓である。つまり、窓が少ない家は、Q値も比較的高く(高得点に)なる。そして、外部と接する外壁面が大きいとその分熱を失う場も増えるので、外壁面を減らす為に部屋の高さを低くして、真っ四角な家にするとQ値では有利になる。
だから最近、形がキュービック状の家や窓が小さくて少ない住宅をPRする住宅メーカーが増えているのである。言い換えれば、息苦しく感じる家の方が、高性能で素晴らしい住宅と言えるかも知れません。
でも、人間は窓があることで光を感じ爽やかな気分になったり、窓を開けて陽気になったりといった精神衛生上の効果が期待出来るのだが、そんなことはQ値のみの世界では無視される。そう、Q値やC値を考えれば、玄関ドアや窓を開けてはいけないのです。これって、バカげてるでしょ~。
そして、建物の形に凸凹の変化があることで、光や空気が通りやすい間取りを実現することが出来るが、Q値を考えればそれは反って数値を下げる要因でしかない。そんなことはナンセンスだし、家や間取りを暮らし方に合せて、設計・デザインする必要もない。
さて、次にC値だが、どうやって測定するのかご存知か?
換気扇など計画的に明けられた穴を全部塞いで、室内の空気をファンで強制的に外に吐き出します。この時に生じる気圧差と風量を測定することにより、隙間面積を出しているのがC値なのだ。
C値は、隙間の面積を対象にするもので、計画的に穴が明けられた換気口などは対象になりません。測定時に換気口や洗面台の配管の穴は密閉して塞ぎます。
実際には、隙間よりこの計画的な穴の方が空気の通り道としては大きくなることがあります。よってC値がいい高性能な?家でも換気のルートが多ければ、隙間がたくさんある状況と同じになってしまうのです。
素人のお客さんが、こうしたことをいちいち考えるのは難しいかもしれませんが、換気や熱損失についてどんな工夫や努力、こだわりを住宅メーカー持っているのかを聞くことは大変重要なことではないでしょうか。
Q値やC値だけでは、暮らせない。暮らし方を決めるのは、性能ではなく家づくりのコンセプトやデザインだと私は思う。風に揺れるカーテンひとつで、涼しさを感じるのが人間なのだ。子供の笑顔や美しい花を見て、温かい気持ちになれるのが家庭なのだ。また、18度で寒いという人もいれば、29度でも今日は涼しいと思う人もいるだろう。そこにあるのは感覚的な快適さであって、絶対値は存在しない。
気密を上げた室内が素晴らしいと思っている人は、春の暖かな日に窓を開けないのだろうか?断熱性が高いからと真夏にダウンジャケットを着て、ジッパーを首のところまで上げている人はいるのだろうか?家はどれだけ暑くても、服(断熱材)を脱ぐことは出来ないのに・・・。
(Q値やC値が高い家の場合、エアコンが付いていない温まった部屋に戻ってきて冷房を効かすには、熱が冷めにくく、反って大きなエネルギーが必要となるのである)
Q値やC値を全否定するつもりは更々ないが、それらを最優先に考える家づくりは、自然の大いなる力を考えない偏った理想であることに気付くべきである。
パナホームやパナソニックを作った松下幸之助が、「家の中で人格は作られる」という言葉を残している。そういうものは、生活や家庭の豊かさから生ずるのであって、数値で表せる性能からくるものではないのでしょうね。私たちは、人間を育てる場(家)を考えなければいけません。
こうした私たちの考えや建築に共感され、施工を希望される方は、ご相談下さい。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。