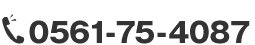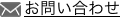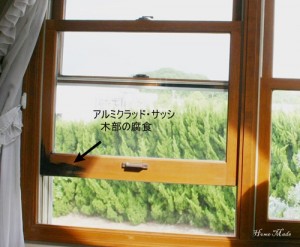どんな職業でも同じだと思うが、普通の場合職を得る時の動機は、お金を儲けたいとか、有名になりたいとかいった自分本位な欲求であることが多い。それは、建築屋でも同じで、お金を儲けて会社を大きくする為に、流行りの新しいデザインや建材を取り入れたり、ローコストで他社と差別化を図ったりする。
でも、そこに大義というものは欠けらも存在しない。
社会に対して自分の仕事がどれ程役に立つか、それが多くの人たちにいい影響を与え得るのか、そんなことを考えて工務店・ビルダーを営む人は、皆無かも知れない。
だって、この長引く不況の中、どうやって生き残っていくかしか考えていないから、理想や理念なんてお金にならないものを追求することは無意味ですらある。私も若い頃は、そうだった。でもねぇ、そういうことだけでは、人間生きていけないって感じるようになった訳さ。
今の住宅業界に欠けたものがどんどん見えるようになってきた。それは、まさに先程述べた自分本位な欲求から生まれた家づくり。流行りのデザインを真似すれば、多くのお客に受けるから仕事も増える。太陽光やスマートハウスを採用するのも同じ発想だ。そこには、何ら理念はない。
皆がやるから、やらないと乗り遅れる。私は、そんな仕事の仕方は間違っているといつも思う。
間違った日本の住宅の在り方を正し、よりよくする為にはどうしたらいいか、それを既存の住宅メーカーがやらないならば、自分自身でやるしかない。そういう已むに已まれぬ思いがあってこそ、努力を重ね、天職というものになっていくような気がするのである。
欧米の本場の職人でしか施工出来ないレンガ積み外壁。超高耐久な住宅を実現する為には、自分でカナダの職人を見つけてくるしかなかったのである。
健康に安全で美しい欧米のドライウォールのインテリア。これだって、当初は日本には職人すら存在しなかった。手間・暇は掛かるが、ビニールクロスより遙かにいいものであることは、皆分かっているのにお金や面倒を考えてどの住宅メーカーも採用しない。
だから、自分でドライウォール用の塗料を輸入し、色まで調合するなんてことをやらざるを得なかった。
最近、私のブログ等を見て相談に来られるお客さんも、他社で建てたがその住宅会社は事業を辞めてしまってどこにも相談するところがない、という事情で電話をくれるのである。そういう已むに已まれぬ思いをお互いが共有してこそ、一致協力して為になる仕事をしようという気持ちになると私は思う。どこに頼んでも出来ることなら、自分の存在意義はないのである。
皆さんの家づくりには、大義があるか。仕事をお願いしようと思っている建築屋さんには、已むに已まれぬ思いというものがあるのだろうか。
家づくりには、高い理念や理想が必要な時代ではないでしょうか。
いくらローコストだって、1,000~2,000万円はするだろう。でも、どんどん悪くなる家では20年あまりで直す気力もなくなり、建て替えの憂き目に遭う。フェラーリが買えるくらいのお金が、ゴミとなるのだ。住宅ローンだって完済したばかりかも知れないし、年齢的にも子供の頑張りに期待する他ない。手間を掛け、品質を追求し、倍の金額の4,000万円を出せば、維持管理次第で100年の歴史を超える建物が建つだろう。
そんな住宅にビルダーの心意気を感じてくれる人は、必ずいるはずだ。
流行を追い、価格の安さだけで勝負するビルダーもいれば、世の中の輸入住宅への理解を深めたいという高い理想や理念の基で、相談する先がなく困っている人たちにも手を差し延べる私たちのようなビルダーも多く存在する。
廃業や事業放棄をしないで、家のメンテナンスを長く一緒にやってくれるビルダーは、どちらだろう。どちらに家づくりをお願いするのかは、あなた次第です。高いハードルを越えて、私たちと価値観を共有出来る人はそうはいないでしょう。でも、そういう情熱を持った皆さんと、私は家づくりをしたいのです。
こうした私たちの考えや建築に共感され、施工を希望される方は、ご相談下さい。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。