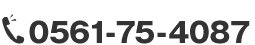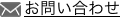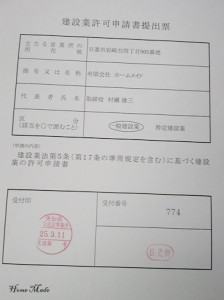先日、とある輸入住宅のお客さんからカナダの洗濯&乾燥機を入れたので排気用のダクト配管を取付け出来ないかという依頼があった。
国産のドラム式洗濯乾燥機だと1台で両方の機能が付いているのが普通だが、北米のものは洗濯と乾燥、それぞれ1台ずつ担当するのが一般的だ。まあ、何れかの機能がおかしくなっても国産のものは高い価格で交換しなきゃいけないんだけど、別々に分かれている分価格は安いし、壊れた方だけ交換すればいいから、経済的ではある。
でも、こんなに大きなものが2つ並んでいると、クロ-ゼット1つ潰さなきゃいけなくなる。(デザインはまあまあだね)
掛け布団や毛布など、全て自分のところで洗う習慣のカナダやアメリカだと、こんなに大きなものが欲しいんだろうね。それにあちらでは外に干せないからね。
排気については、国産のものは湿気った空気を水に戻して洗濯排水の管に出してしまう方法(水冷式)があるようだが、北米の乾燥機はダクト排気。どっちがいいかは分かりませんが、北米のものの方が構造はシンプルだろうね。
何れにしても、こういう依頼が来るっていうのは、輸入家電を施工しているホームメイドだからなんだろうなぁ。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご利用下さい。