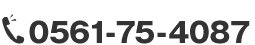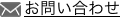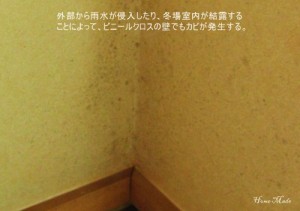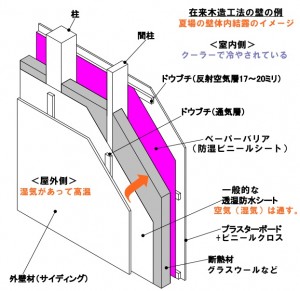今日、住宅ローンを含めたフィナンシャルコンサルをするという方が、営業活動にいらした。その話の中で、クライアントのご家族の中には、消費税アップ前に家づくりを検討している人がたくさんいらっしゃるというお話を聞いた。
例えば、中川区の分譲物件を検討中という方は、3000万円で土地付きの一戸建てを買いたいと考えているらしい。そこで、こういう状況について意見を求められた。
私ならば、こういう方はまだ購入を急ぐべきでないと思います。
そういう方の多くは、住宅一次取得者と呼ばれる、若いファミリーでまだ十分な蓄えもなく、同じように家賃を払うなら、その支払いを住宅購入のローンに当てたいと考えている方なのです。
つまり、住宅というものに対して、あまり知識を持たず消費税が上がる前に安く買いたいという動機から、価格という要素に高い優先順位を当てているのが、一般です。
ただ、ここでよく考えて欲しいのは、名古屋市内で土地付きの新築物件を購入する時、3000万円という価格はあまりに安い。これを、企業努力でコストを削減し品質は平均以上と捉える人は相当のお人よしだろう。
数百万円単位でコストを削減出来るのは、大量生産が可能な工場生産品だけである。中小の業者が先進のコスト削減技術を駆使することなど不可能なのです。
中小の建売業者や不動産屋では、自分たちの利益を圧縮するにも限界があるし、自分が損をしてまで売るというボランティアを誰もやろうとは考えない。ならば、取り敢えず見てくれをよくして、その中身を安もので施工するか、施工に手を抜く以外に方法はない。
現在、日本の平均築年数が25~26年と言われている。では、この物件の品質は日本の平均より高いというふうに想像出来るだろうか。賢明な方ならお分かりだろうが、平均以下の家づくりとなっていることは、ほぼ事実だろうと思う。
ということは、この物件は、平均耐用年数の25年維持することが出来ないリスクが高いということに他ならない。それも、長期の住宅ローンは、残ったままで・・・。
また、必要な利益をもらわずに販売している分譲屋さんだとすれば、それこそ将来メンテナンスに割ける時間的・金銭的余裕もなく、もしかしたら何年後かには会社が存続していないかも知れない。
維持管理が十分でない建物は、それこそ長く住み続けることは難しい。
輸入住宅ブームが去った昨今、ホームメイドにメンテナンスの相談に来られる方の大半は、ビルダーが倒産か既に事業から撤退した為に困って来られる方たちなのです。当時、「輸入住宅は安く建てられる」とPRした業者もありました。
若い皆さんは、これを最後のチャンスと考えているかも知れませんが、もう少し貯蓄を増やして、もう少し家について勉強し、それから自身の納得出来る素敵な家づくりを目指すべきだと思います。
だって、外装に安い材料を使えば、10年もすれば、屋根や外壁の塗り替えに100~150万円の費用が掛かることになります。住宅ローンを支払うのに目いっぱいなのに、10年毎に多額のメンテナンス費用を払うことが出来ますか?
格安でお値打ちな物件など、世の中にはあり得ません。自分の社会的キャリアをもっと高く積み上げて、その上でそのキャリアに見合う家づくりをすることが、無理のない豊かな暮らしを楽しむ唯一の方法なのです。
世の中の仕掛けにまんまと乗せられるのは、自分の立ち位置が見えない人だけです。そういう消費者に支えられて住宅業界が成り立っているのですが、逆に言えば、そういう人がいるから一向に住宅業界の質が上がらないのです。どうぞ賢明な家づくりを考えてみて下さい。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによっても、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご利用下さい。