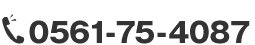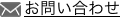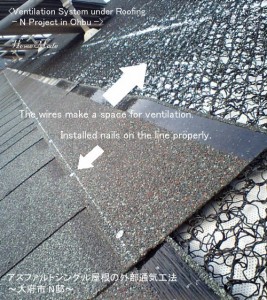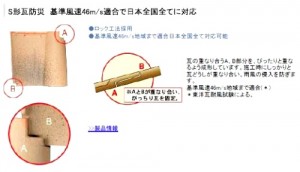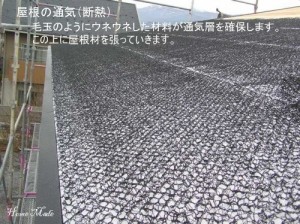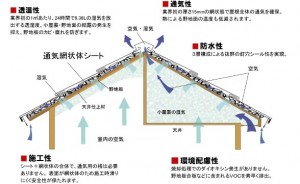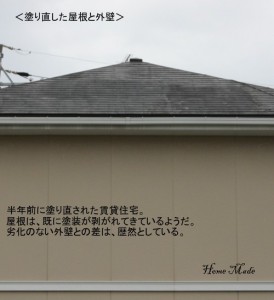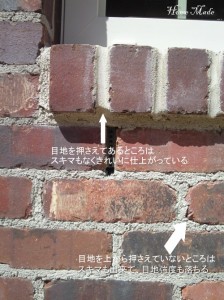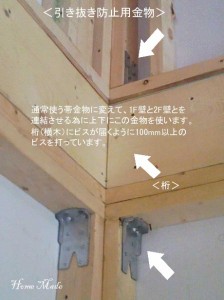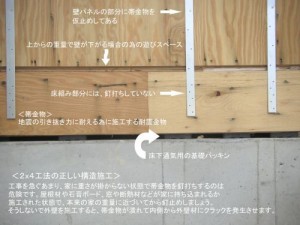エナメル・ブラウンのカラーが、何ともレトロチックなこの薪ストーブ。
この色以外に、ロートアイアンや耐熱塗装のブラックのデザインなんかもあるんです。ほんとこのストーブは、古い感じをうまく表現しているなぁと思います。
本体横にデザインされた網目模様やフロントドアのエレガントなアーチワークが素敵です。
本体サイズは、意外に小さくて65cm程度しかありません。そのコンパクトさが、更にレトロさを感じさせてくれると共に、日本の住宅サイズにはピッタリかも知れません。
機能面もしっかり考えられていて、本体下にはアッシュ・パンもありますから、燃えかすや灰の処理も簡単です。
日本での適用があるかどうかは分かりませんが、メーカーはHPでライフタイム・ワランティ(永久保証)を謳っていますので、堅牢さも十分でしょう。だって、重さも130kg(本体内の耐熱レンガ込み)もありますからねぇ。コンパクトでも搬入・据付は大変です(笑)
こうしたデザインの資材の調達や建築をご希望の方は、ご相談下さい。
※ この「お知らせ」ページは、「カテゴリー」や「タグ」のキーワードをクリックすることによって、興味のある関連記事を検索頂けます。どうぞご活用下さい。尚、写真及び記事の著作権は、当社に帰属します。無断での転載・引用はご遠慮下さい。